
転職ドラフトでも人気のスタートアップ、カミナシは、工場や宿泊施設、設備保全など、現場業務のDXを実現するプラットフォームを運営。2020年に現在のプロダクトをローンチした後、2024年からマルチプロダクト化を急速に進め、いまでは5つのプロダクトで帳票管理から設備保全、研修、コミュニケーションと幅広い領域のDXをカバーしています。
これらのプロダクトの開発・運用を支えるのは、社内に40人近くいるエンジニアの皆さん。今回は、「ノンデスクワーカー」の業務現場にフォーカスしたプロダクト開発のやりがい、スタートアップならではの仕事の魅力などについて、CTO原さんとEM吉永さんに伺いました。カミナシに興味のある方はもちろん、スタートアップへの転職が気になっている方もぜひご一読ください!
株式会社カミナシ
取締役 CTO 原 トリ(写真左)
ERPパッケージベンダーR&Dチームにてソフトウェアエンジニアとして設計・開発に従事。その後クラウドを前提としたSI+MSP企業での設計・開発・運用業務を経て、2018年Amazon Web Services入社。AWSコンテナサービスプロダクトチームでのサービス改良、および同サービス群を中心とした技術領域における顧客への技術支援や普及活動をリードした。2022年4月 カミナシ入社し、2022年7月 執行役員CTO、2023年4月に取締役CTOに就任。
エンジニアリング本部 CTO室 Engineering HR 吉永 聰志(写真右)
3D CADのデータ変換ソフトウェアの開発チームにてエンジニアとして開発に従事。その後創業フェーズのスタートアップにエンジニアとして参画し、約10年間在籍した。会社の成長とともに、役割をエンジニアリングマネージャーにチェンジ。HR Techの会社における開発組織のマネージャーを経て、2022年12月にカミナシに入社。
エンジニアもユーザーの現場訪問を重ねて課題を実感
ーーカミナシで働く魅力について、まずは一言ずつお願いします。
吉永:お客様に価値を提供している実感がしっかり得られることと、チームの裁量でプロダクトをいかようにも進化させていけることは大きいと思います。とくに前職で「お客様の顔が見えない」「自律的に物事を決められない」といったフラストレーションを抱えていた人にとっては、手触り感を満喫できる環境です。
原:自分たちの技術を駆使して、ユニークな課題を解くことに挑戦できるのはやっぱり楽しいですよね。そういう機会がゴロゴロある会社です。
ーーユニークな課題とは?
原:たとえば、工場などの現場でPCやタブレットを使うときのユーザー認証はどうすればいいのか。ゴーグルやグローブを着けて作業している人は、顔識別や指紋認証を使うハードルがとても高いですし、複数人で1台の端末を共有している場合は、パスワードマネージャーを利用するわけにもいきません。現場にとっては超クリティカルな課題ですが、一般的なWebサービスの世界で仕事をしているエンジニアであれば普段強く意識することのないタイプの課題だと思います。
吉永:ノンデスクワーカーの業務課題以前に、業務環境や内容そのものに馴染みがない僕らとしては、お客様先を訪問するたびに学びだらけです。僕自身はまず新しい知識に触れられること自体が楽しいですし、お客様の課題を解決するためにエンジニアとして何ができるのか、もっと貢献できるエンジニアになるためにはどんな専門性を高めていけばいいのか、ゼロベースで考えられる点に面白さを感じています。
ーーエンジニアもお客様先を訪問するのですか?
原:新規プロダクトの開発中などは相当な回数行っていますし、既存プロダクトでもお客様の抱えている課題を理解するためには、直接行くのが一番早いですから。現場の温度や湿度を肌で感じ、お客様の作業を自分の目で見て、初めて分かることがたくさんあって、それがプロダクトのクオリティにつながります。

お客様は何にどう困っているのか、言語化できないことも多いんです。もちろん、営業やカスタマーサクセスを通じて得られる情報もたくさんありますが、いま何を優先し、どんなアプローチで開発するのかを判断するためには、作り手の視点で一次情報を取りに行くステップを大切にしています。
ーーユーザー現場のペインをリアルに感じながら、開発に臨める環境なのですね。
原:導入効果に関しても、お客様との信頼関係構築に強みを持つカスタマーサクセスのおかげもあり、生の声に触れられる機会がたくさんあります。「カミナシを使って現場で業務改善した若手が社内の賞をもらいました」という話が入ってきたり。
吉永:あれはテンション上がりますね。
原:お手紙をくださるお客様もいらっしゃいました。「御社の製品を入れて取り組み始めてから、会社がこんなふうに変わりました」と。やりがいを噛み締められる瞬間が多い会社ということは、間違いなく言えると思います。
強いオーナーシップを持つ人が動きやすい環境を追求
ーーカミナシで活躍できるエンジニア像とは?
原:一言で言うなら、「オーナーシップを強く発揮できる人」です。自分の手がけるプロダクトに愛着を持ち、真剣にお客様のことを考え、ユーザーニーズによりマッチするプロダクトへと進化させるべく、自身の専門性を軸にその領域外にも積極的に染み出していける人。そんな人が力を発揮しやすいよう、組織設計も工夫しています。
まず、現在5つあるプロダクトごとにチームを編成していて、EMもメンバーも兼務はなし。その分、採用活動はハードになりますが、各自が「自分のプロダクト」に集中できる環境を大切にしています。
もう一つ、こだわっているのは、フロントエンドやバックエンドといった職能別に組織を分けないこと。ジョブタイトルも全員「ソフトウェアエンジニア」です。たとえばあなたがバックエンドを得意分野とするソフトウェアエンジニアだったとして、必要ならフロントエンドやデザイン、プロダクトマネジメントの領域にまで相互に踏み込んでいきやすいんです。
ーー働く環境次第では、「領空侵犯」ともとらえられそうです。
原:その点でフラストレーションを感じた経験がある人って、たぶん業界にたくさんいるんじゃないでしょうか。プロダクト開発中に「フロントエンドチームはもう準備ができたけど、バックエンドチームの作業が遅れているから、リリースが1カ月延びそう」とか、あるあるですよね。カミナシでは、「ニーズの高いサービスを少しでも早く市場に出すには?」という発想で、フレキシブルな動きを取ることもしやすい環境です。
サービス・プロダクト組織のなかだけでなく、より広い範囲に染み出すこともよくあります。たとえば、「プロダクトの持つポテンシャルを、セールスによりうまくお客様に伝えてもらうにはどうすればいいだろうか」を言語化するために、自らカミナシが出展する展示会のブースに足を運んでお客様と会話してみたり。
話していると、本当に伝え方次第、言葉の選び方次第で、聞き手の反応が変わることが分かります。そうやってセールスやマーケティング担当者が見ている景色を知っていくと、どんなふうに彼ら彼女らとコラボレーションすれば成果を最大化できそうか、自分なりのアイディアも生まれてきます。エンジニアが展示会に参加している様子は、カミナシだと定期的に見かけますね。
ーー開発者でありながら、自分たちのプロダクトがユーザーに届くまでのプロセスにも意識を向けているのですね。
原:染み出しまくることで、視野が広がり、視座が上がっていく。エンジニアに限らず、会社組織で活躍していくうえで大切なポイントですよね。「染み出し」は、圧倒的な成長スピードを出すための重要なヒントの一つでもあるんだろうなと感じます。
会社全体で情報の透明性が確保されていることも、社員がオーナーシップを持って動きやすい環境をつくるうえで重要です。プロダクト開発を通じて、お客様にいかに価値を提供できるかを追求する人にとって、ステークホルダーで同じ景色を共有して走ることには大きな価値があります。カミナシでは、経営会議の議事録なども全社に公開されていて、経営会議参加者がそれぞれの視点から賛成や反対の意見を述べていることも丸見えです(笑)。
一つの大きな決定の裏にはいろいろな意見があって、ときにはメンバーの意見が真っ二つに割れることもあります。でも、十分に議論を尽くした後は、たとえ個人的には反対の立場であっても、結論を尊重し、コミットする。まず経営メンバー自身がそれを実践し、その姿を全社に見せていくことで、風通しのよさを保っていきたいですね。
互いの見ている景色のギャップを対話で埋める
ーーエンジニアリングのチームには、どんなバックグラウンドの人が多いですか?
吉永:かなりバラエティに富んでいて、コンピュータサイエンスを専攻し、修士や博士を持つ人たちもいれば、異業種経験者もいます。たとえば、コンビニ業界から転身してエンジニアキャリアを作ってきた人、かつて革職人の弟子だったという人もいますね。SIerからカミナシに転職して来てくれた人ももちろんいます。

原:皆さん、主力で活躍してますね。それぞれキャラクターもユニークで、社内にファンがいっぱいいます。
吉永:雑誌の編集者をしていた人や工場勤務の経験がある人もいます。工場経験者は、製造ラインのオペレーション改善について、社内の勉強会でみんなにシェアしてくれたこともあります。
ーー本当に多様ですね。マインド面では、カミナシのエンジニアらしいカラーはありますか?
原:協働するメンバー同士、対話をしっかりして認識のずれを埋めようとするところは、カミナシらしさかもしれません。とくに役割の異なるメンバー、たとえばエンジニアとプロダクトマネージャーやデザイナーといった人たちが組んで仕事をしようとすると、「いいプロダクトをつくる」という目的は同じでも、見ている景色はそれぞれ違います。でも、そこで噛み合わないまま進んでしまうと、生み出すプロダクトのクオリティにもろに響くんです。
「いま、会話ずれてるよね?」と気づいたらいったん立ち止まり、お互いの意見を背景含めて理解したうえで、最良のソリューションを探っていく。面倒なプロセスですが、しっかり実践できるメンバーがそろっていると思います。
ーー視座の高さを感じるお話ですね。
吉永:といっても、堅い雰囲気は全然ないですよ。社内のSlackなんかかなり……
原:よく言えば、遊び心? 謎のスタンプがどんどん増えてますね。僕はもはやみんなにフリー素材扱いされてます(笑)。
吉永:カジュアル面談後に集めている感想でも、面談者の人柄に好印象を持ち、「一緒に仕事をしたら面白そう」と感じてくださる方が多いようです。言語化が難しいのですが、初対面の場でも伝わる何かがあるのかなと。気になる方はぜひ、カジュアル面談に確かめにきていただけるとうれしいです(笑)。
ゲームが変わる瞬間に主人公として立ち会える
ーースタートアップに興味を持ちつつ、いざ転職となるとためらいを感じる人も少なくないと思います。お二人にとって、スタートアップで働く醍醐味とは?
原:大企業にはないスピード感、ときには会社が一気に変わっていくダイナミクスを味わえることです。たとえば、カミナシは昨年から今年にかけてマルチプロダクト化を進めてきましたが、プロダクトが増えればセールスの手法も、カスタマーサクセスの進め方も、コーポレートの仕事の仕方も変わる。そういう「ゲームが変わっていく」瞬間に立ち会える、それも変化に巻き込まれるのではなく、一人ひとりが主人公としてプレイできることは、人生のなかの得がたい経験になると思います。
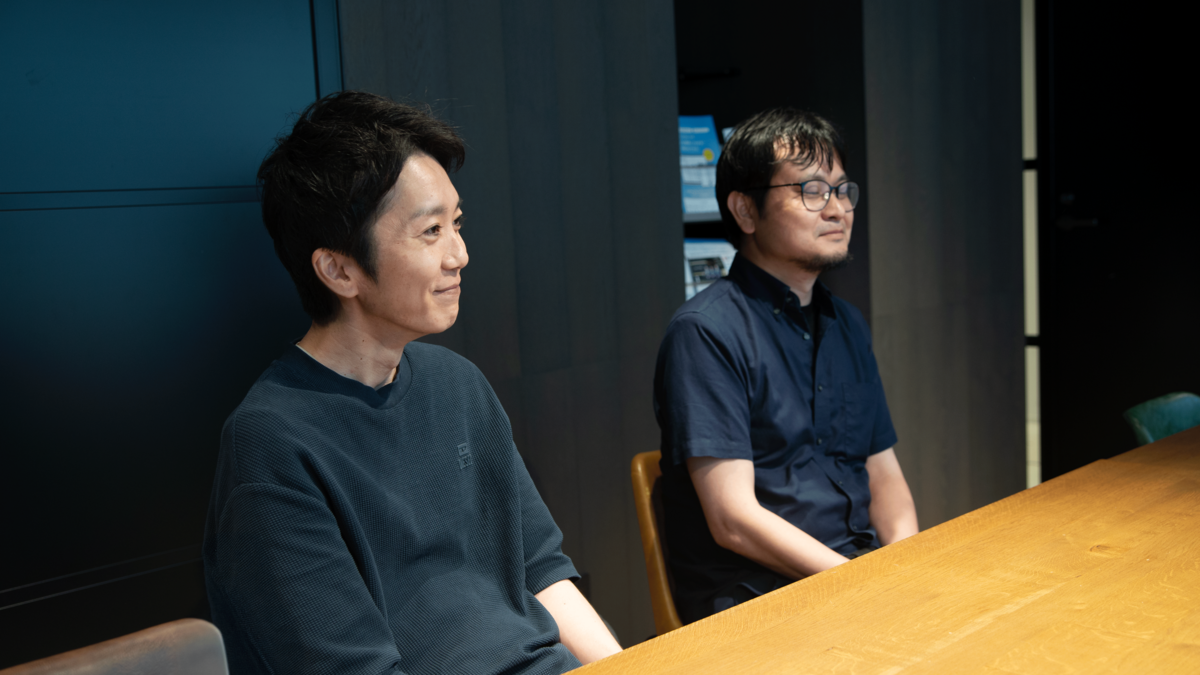
吉永:まだまだ発展途上の会社ですし、これからどんな変化を遂げていくのか、いろんな可能性があります。カミナシが掲げるミッションやビジョンが実現されたら、それはつまり MicrosoftやAppleのような世界を変えた企業の一つにカミナシがなっている未来だってあるわけです。そんな大きなうねりを生み出す一人になれるかもしれないと思ったら、ワクワクしますよね。
原:カオスのなかで自ら方向性を示せる人が次のフェーズをリードしていく、それがリアルに起きるのがスタートアップですから。いまのカミナシの企業規模なら、その気になれば会社全体の方向性すら変えられると思います。直接CEOと会話をして優れた提案ができれば、最終的に採用される可能性が十分ある。もし大企業で社長室に乗り込もうとしたら、警備員につまみ出されちゃうでしょうけどね。
ジェットコースターのような変化を楽しめる人、チャレンジャーであり続けたい人にとって、スタートアップは密度の濃い体験ができる環境です。続きはぜひ、カミナシのカジュアル面談でお話ししましょう!
(取材・文/中名生 明子)
